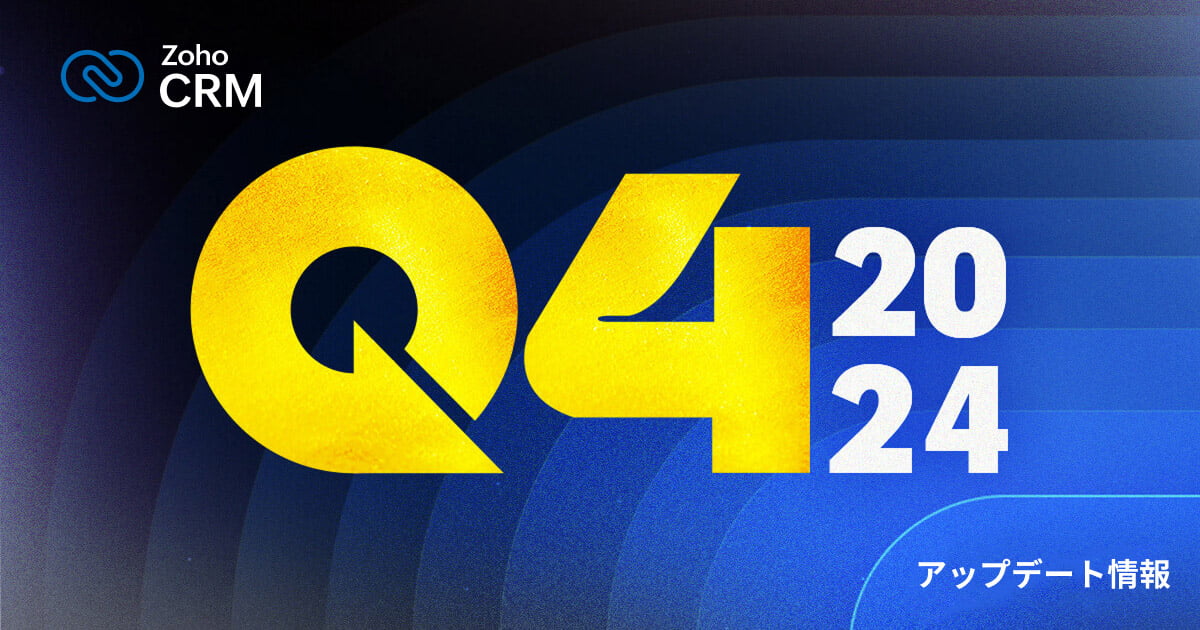「 安かろう、悪かろう。」これは異常に低価格な商材に対し、誰もが頭に過ぎる言葉だ。逆もまた然り、高ければ「 すごいもの(素晴らしくあるべき)」と考える。
自動車であれば、300万、500万、1,000万と価格が上がれば性能も上がり、ラグジュアリー感も増す。
巷で提供される商品・サービスのほとんどが、この法則に当てはまるが、例外的に当てはまらない商材の一つ。それが「 CRM 」をはじめとするビジネスツールだ。
ビジネスツールの提供価格に潜むカラクリは、理解こそすれば単純だが、見抜きづらい。しかしこれに気付き「 いまいちなCRM 」に大金を投じていた企業が今、「 高性能な格安CRM 」に乗り換えを進めている。
ビジネスツールの価格設定に潜むカラクリ
商品の価格は、①原価 ②需要 ③競合状況 の3つを踏まえ設定される。このカラクリを理解すれば、あらゆるビジネスツールの選択が賢く行える。
勘の良い人であれば、この時点で「 世界規模 」で検討しなければ高性能な格安CRMには辿り着けないことに気づくだろう。その理由は、後述の通りだ。
ビジネスツールの原価は、その開発を行う「人件費」が主だ。もちろん、営業をはじめとした人件費率が高い企業も在るが、これが価格設定を異常に引き上げることは明白である。ここで注目すべきは、自社開発か否か。他社開発や他社商材のレーベル販売(他社が提供するツールを自社名で販売する)の場合、その原価が自社開発の倍以上になることもザラだ。また、自社開発であっても、その主要開発地は重要なポイントになる。高い技術力・先進ノウハウを備え、かつ人件費の安い国で開発していることは、「 高性能な格安CRM 」に必須の条件だ。
原材料が不要なビジネスツールは、販売数が1つでも、100万でも原価は変わらない。そのため、一定数の販売規模が確保できるマーケットが広がれば、その分安く提供できるカラクリだ。価格が下がれば、その分販売しやすくなるため、CRM提供企業はマーケット確保に注力する。
すると、「 シェアが多いCRMは、割安で提供される 」と着地できそうだが、そう単純ではない。競合状況は、販売エリア考えると分かりやすい。アメリカや日本など、先進諸国で主に展開されている場合、釣り上げても一般的な価格であるように見えるため、ここで利益を積む戦略も存在する。
これら3つの価格設定のカラクリを理解すると、「 高かろう、良かろう 」の法則がビジネスツールに適用されないことは明白である。
人件費
需要
競合状況
高性能な格安CRMで、企業成長の「 促進剤 」を十分に整える。
CRMは今や、ビジネス成長に欠かせない促進剤だ。2021年を迎え、デジタル化に懐疑的な経営者や管理職は少数派となった。しかし所謂、一流と呼ばれる経営者でも価格設定のカラクリに翻弄され、CRMという経営の促進剤の選択を誤り、行き詰まる。なぜなら、「 格安 」は一目瞭然だが、「 高性能 」を見抜く難易度が高いからだ。
そこで、公正な視点から「 高性能 」を見抜く重要な要件を3つ定義する。
まずは当然に、機能性だ。CRMとしての基本機能を備えることはもちろん、自動化や分析など、十分な機能を備えていることは前提である。
次にカスタマイズ性にも注目すべきだ。CRMは、利益を生み出す営業部隊の活動プラットフォーム。つまり、戦士の装備品だ。当然、動きづらい既製品よりも、カスタム・オーダーメイドの装備は、パフォーマンスが出やすい。
優秀と万能は、似て非なるものだ。必要なビジネスツールは、企業によって異なる。また、企業の「 今 」には優秀なツールも、未来の要件まで満たすことはできない。必要なのは、機能アップデートが行えること。また、必要に応じて別のツールとつなげられること。つまり、企業の進歩に併せて進化を遂げるポテンシャルを秘めたCRMであることが、高性能である最後の要件だ。
この高性能なCRMを格安で入手することで、必要なすべての社内メンバーに行き届けられ、企業成長の「 促進剤 」としてはじめて十分な効果が発揮される。
実際、マーケティング活動における自社の内製化を支援する、インハウス型支援ビジネスのパイオニア的存在 アタラ合同会社のCEO杉浦氏は、「格安のCRM」で高い「促進剤」効果を発揮している。
「事業の成長に伴い、コストや運用管理、拡張性の面で実情に合わなくなっていた。そこで、Zohoのクラウド型CRMシステム「Zoho CRM」にリプレース。CRMのコストを約1/4に削減できたことに加えて、各アプリケーションのデータ連携による経営の可視化やデータ活用の推進、ビジネスの変化にシステムを素早く柔軟に対応できる体制の整備など、多くの効果を得ている。」
「CRMのコスト増大と複雑化がビジネスの足かせになっていました。
1/4のコスト削減と経営の可視化・データの有効活用を同時に実現しました。」
アタラ合同会社
CEO 杉原 剛 氏
高くて有名なCRMに騙される構図
CRM提供企業は、高性能を見抜く難しさを巧みに利用する。豊富な機能で在ることを売りにしているが、実態はCRMとは別に第三者サービスを組み合わせ、さらに追加料金を求めるケースは多い。また、CRMをカスタマイズすると謳いながら、新たなシステムを構築して莫大な費用を求めるケースもある。
本来、中小から大手企業まで、あらゆる企業の人的負荷の軽減と戦略的思考の下支えであるべきCRMをネタに、その背後で「 搾取 」の文字が蔓延るケースも少なくない。
もちろん、CRMをいかに活用するか、そのノウハウを売りにコンサルティングを繰り広げる企業も多く、客観性に基づく適切な判断と短期的な結果へと導くものだが、これを搾取と取り違える企業も多い。これは、投資が十分に結果として還元される。
しかし、先のツールへの不必要なまでの投資を求める搾取では、結果に還元されることがない。それは、「 高性能なCRM 」に必要な要件からも明らかだ。しかし、有名大手CRM提供企業でも、こうした搾取が平然と行われている。
伸びる現代企業が求めるCRMトレンド
CRMには、顧客管理特化型とそれに営業支援強化を組み合わせた2種類が在ることをご存知だろうか。
顧客管理特化型は、顧客情報を記録するデータベースであることに特化し、一拠点集中の管理を実現する。エクセルをはじめ、個人ファイル管理による俗人的な環境から一拠点集中にすること。これは多くの日本企業がデジタル化の主要目的として掲げる課題だ。しかし、一拠点集中は、正しい進行の道を辿れば数ヶ月で完了する。そして、その先に現れるのは、飽くなき「 自動化 」と「 可視化 」への探求だ。
これは、CRMだけでは補えず、SFA(営業支援)が必要になる。このSFAを備えた営業支援強化型のCRMこそ、令和のトレンドだ。
例えば、インターネットを活用したオンライン英会話サービスで業界を牽引する株式会社レアジョブは、営業力強化や業務効率化を図るうえで「 販売プロセスにおけるデータの分断 」を解消するため、Zoho CRMを導入した。圧倒的な低コストによって、ランニングコストが約1/3に大きく削減された。CRMは機能が豊富で難しいか、機能が少なく単純の2極化しがちな傾向がある。あらゆる自動化機能を駆使し、「こうしたらもっと効率化が図れる」という現場の声を即座に具現化し、年間30人月分の工数が削減された。
「ランニングコストを約1/3に削減。
さらに、自動化の幅が広がり年間30人月分の工数削減を達成。」
株式会社レアジョブ
御園 裕太氏
誰もが革新的と唸る。Zoho のビジネスと収益モデル
Zoho(Zoho Corporation Private Limited) は、1996 年に創業したインドのIT企業であり、CRMをはじめとした営業、マーケティング、ヘルプデスク、ドキュメント、会計・経理・人事などのバックオフィス系など、ビジネスに必要なあらゆるサービスを50種以上、提供している。

その開発は、すべて社内の正規社員が行う。現在、10,000名を超える社員が在籍し、ツールの開発とカスタマーサポートがその多くを占めている。これは、Zoho の掲げるビジネスモデル「Marketing through Engineering(エンジニアリングを通じたマーケティング)」に基づいた戦略。つまり、ツールの成長による顧客への利益還元を通じて、世界中のビジネスに貢献するマーケティングである。
実際、Zoho CRM は、高い機能性を備えながら、月額¥1,440(税抜き・年間契約の月額換算)から利用できる。もちろん、初期費用などのイニシャルコストやオプション追加などは不要である。
さらに、サービス利用単体に留まらないのが、Zoho 最大の強みだ。Zoho で提供されるほとんどのツールが、シームレスに連携する。これには、全社で利用を統一できるのは嬉しいという声も多く上がっている。Zoho は、ビジネスのOS(オペレーション・システム)として、世界6,000万人を支えている。
その背景には、Zoho の価値想像に対する飽くなき探究心が在る。各国のビジネスに適合した価値想像を実現するため、自社ツールの他言語対応や機能拡張はもちろん、3rd Party (サードパーティ/第三者ツール)へのシームレスな連携にも多くの人員を充てている。
これを実現するため、現在、10,000名を超える社員数でありながら、非公開企業としての姿勢を貫ぬく。この背後には、提供するサービスより「 利益 」を優先せざるを得ない状況を回避し、ユーザーへの価値想像を追求する姿勢をこれからも遵守していく。

世界250,000社が利用している、Zoho CRM をぜひ無料でお試しください。
有償プランを
無料アカウントを作成する
15日間お試しZoho CRMが
製品の特徴を確認する
選ばれる理由Zoho CRM
機能を確認する
機能概要