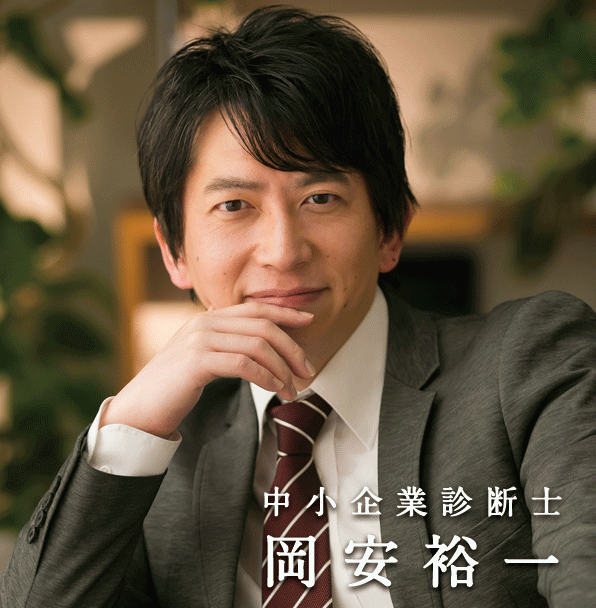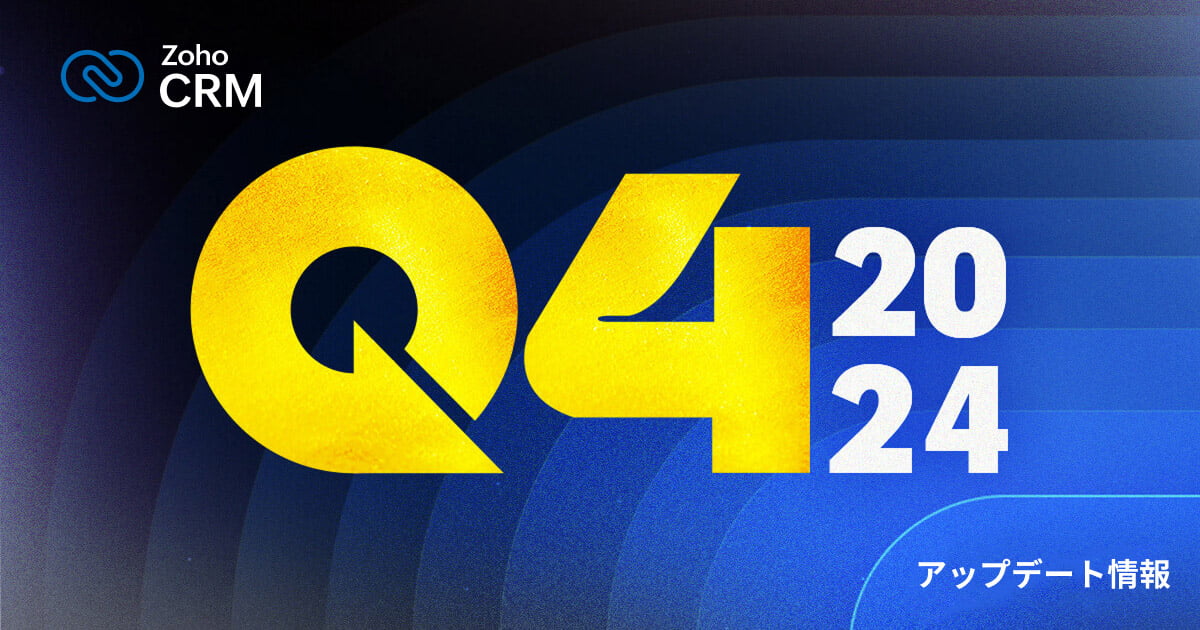メールマーケティングツールとは
メールマーケティングとはお客様にキャンペーンやお買い得情報等をメールで送信して勾配を促すマーケティング手法を指します。そして、メールマーケティングツールはその作業を自動で実現するツールのことを指します。自動でメールを送れるだけでなく、顧客情報や購入履歴を紐づけることでターゲットを絞った広告送信を行ったり、広告の内容を変更したりできます。
メールマーケティングツール導入の効果
メールマーケティングツールを導入せずとも広告メールは送ることができます。例えば、Excelで顧客リストを管理しておき、対象者に対してBCCなどの方法でメールを送る方法です。メールソフトのスケジューラーを利用すれば、時間を指定した送信もできるでしょう。しかし、それでは大きな人的コストやセキュリティリスクがあります。そのため、メールマーケティングツールを導入することで以下のようなメリットを得ることができます。
配信ミス・個人情報漏洩リスクの削減
1つ目は配信ミスや個人情報漏洩リスクの削減です。上記のExcelで管理する方法であれば、メールを送信する都度、人や会社を選んでメールを送らなければなりません。1つずつ手動で選ぶとなるとどうしてもミスが発生します。例えば、本当に必要な人に送らずに、誤った人にキャンペーンメールを送ってしまう、BCCでなくTOでメールを送信してしまうなどです。特に誤ってTOでメールを送ってしまうと影響範囲は自社だけでなく、情報漏洩されてしまった会社にも及びます。
メールマーケティングツールを導入することで、ツールに格納してある顧客管理データベースなどから自動で配信対象者を選別し、メールを送ることができます。配信対象者の選定方法も多くの設定が可能であり、手動で対象者を選別する必要がなく、配信ミスや個人情報漏洩のリスクを低減できます。
業務の効率化・省力化
2つ目は業務の効率化や省力化が行えるということです。Excelなどで顧客リストを管理してキャンペーンメールを送っている場合、作業者は対象リストを絞り込み、配信対象者をBCCの宛先リストにひとりずつ追加し、メールの文章を検討し、スケジュール設定を行うという多くのステップを踏まなければなりません。特に配信対象者を宛先リストに入れるには通常のメールを送信者を選ぶのと同じく多くの時間がかかってしまいます。
メールマーケティングツールを導入することで、配信対象者のリストの絞り込みからBCCの宛先リストへの追加を、条件設定のみを実施するだけでほとんど自動でやってくれます。条件設定も様々な方法があり、高度なメールマーケティングツールによっては顧客情報や顧客の購買履歴を参照した条件設定も可能です。また、スケジュール設定などもメールソフトに比べて簡単です。他にもツールによってはメールのテンプレート文を保存しておくなど様々な効率化メソッドが用意されています。
このことからメールマーケティングツールを導入することで業務の効率化・省力化ができるようになります。
マーケティング効果の最大化
3つ目はマーケティング効果の最大化が見込めるということです。人の手で設定したメールで効果を測定するのには限りがあります。例えば、開封した人の数を測定することも、1つずつ数えていけば分かりますが、かなり大変でしょう。また、統計的なデータを取るのはもっと大変です。
しかし、メールマーケティングツールを導入することで様々な効果を測定できます。例えば、メールの開封率を測定することもできますし、クリック率を測定することもできます。開封率やクリック率は顧客のより深い関心度合いを図るための指標としてメールマーケティングにおいては1つの大きな指標になります。また、効果を測定した後の改善活動も行うことができます。「送信者情報」、「件名」、「本文」、「配信曜日」、「配信時間」などをツール内で管理をしているため、それらの内容を精査することで分析活動も行うことができます。過去のデータから迅速にPDCAサイクルを回すことができ、メールマーケティングにおけるマーケティング効果を最大化することができます。

メールマーケティングツールの種類
ここまでメールマーケティングツールを導入するメリットをご紹介しました。ツールを導入することでミスの低減や業務効率化、マーケティング効果の最大化など様々な効果を得ることができます。そのようなメールマーケティングツールですが、様々な種類のツールが存在します。ここではメールマーケティングツールの種類を紹介します。
PCインストール型のソフト
1つ目がPCインストール型のメールマーケティングツールです。ソフトを買いきって利用するツールですが、低コストで利用できるのが特徴です。しかし、近年では低価格な月額料金のメール配信サービスが多くありますので、あまり利用されなくなっております。しかし、顧客管理用のデータベースや顧客情報からメーリングリストを作成する機能など、一定以上の機能を持ったツールがほとんどであり、単に運用だけ考えると十分な場合もあるのが、このレベルです。
ただし、特定のPCにインストールして使用するため、企業として利用する場合には専門のPCや部門共通のPCを用意してインストールしなければならないため、管理に手間がかかります。また、そのソフトウェアをインストールしたPCが故障してしまったりしてしまうと運用が停止してしまうことになり、安定運用には課題が残ります。また、顧客情報などデータの共有が難しかったり、他のシステムと連携が難しかったりするため、組織や企業として長期的な業務効率化を目指して利用するのは難しいのがこのレベルです。
無料メルマガスタンド
2つ目が無料のメルマガスタンドです。この無料のメルマガスタンドは名前の通り、無料でメルマガを送信することができます。
単にメールを配信するだけであれば、問題なく利用ができ、到達率なども高い水準で保つことができます。しかし、メールアドレスの自動登録の機能がないため有料で代理登録を行う必要があったり、ある時点(資料請求日・申し込み日・初回購入日など)をスタートラインとして、事前に用意していた複数のメールを、設定したスケジュールに沿って順次配信する仕組みであるステップメールなどが使えないなど、ビジネスで利用するのは難しくなってきております。また、無料ということもあり、意図しない広告が挿入されたり、登録リストを自社のリストとして管理できなかったりといったネガティブな側面にも注目が集まっており、最近は企業で使っているところが減ってきています。
本サイトでも企業利用として、無料メルマガスタンドを利用するのはお勧めしておりません。
メール配信サービス(クラウド/ASP型)
3つ目がクラウド型やASP(アプリケーションサービスプロバイダ)型のメール配信サービスです。近年、メールサービスとしてのみ利用するのであれば、このパターンが多くなっております。このメール配信サービスは端的にいうと、無料メルマガスタンドの有料版を利用するイメージになっております。
しかし、無料版のツールと比較すると、一斉に送信できるメールの件数が格段に増えていた李、ステップメールが送れるようになっていたり、開封率やクリック率の調査ができるようになっていたり、配信リスト管理がより細かくできるようになっていたりと効果測定のためのさまざまな機能を有しているものが多く、単に機能を比べると、無料版のツールでは比較にならないほどの機能を備えております。
それぞれのメール配信サービスで大きな違いはありませんが、配信方法の設定など細かな仕様の部分でそれぞれのメール配信サービスで違いがあります。自社の特徴を良く精査し、機能が一致しているかを確認するとともに将来的な拡張性(顧客リストとの自動連係など)を意識したツール選定を行えるように意識もできるとよいでしょう。
また、メール配信サービスはもともとアフィリエイター向けや情報商材系のサービスを出自としているものなどもあり、リスト管理の仕組みなどに癖があったり、企業のメールサーバーによっては、配信元がブラックリストと判断されることもありますので、サービスの選択には注意が必要です。
ツールを選ぶポイント
メールマーケティングツールには現在様々な種類のツールが出ています。これらを比較するとなると配信可能な件数、ステップ数、メールのテンプレートの保存件数等様々な比較要素が出てくると思います。その一方で、比較担当者が見落としやすいポイントもあります。ここではツールを選定する人が忘れやすいポイントを紹介します。
運用担当者の人数
1つ目のポイントは運用担当者の人数に応じた運用プロセスが確立できるかというところです。いかに理論上は効率のよいシステムが作り上げられたとしても、実際に運用できなければ意味がありません。
例えば、メンテナンスは営業担当者全員で実施を行い、配信リストの管理はメール配信担当者が行うといったプロセスを考えます。いくらメール配信担当者がきちんと配信リストを管理していたとしても、営業担当者がきちんと顧客リストを管理していなければ、最新データが反映されません。そのため、もともと理想としていたプロセス、すなわち最新のデータを元にしたメール配信など絵にかいた餅になってしまいます。
この状況を打開するには大きく2つの方法があります。1つ目は営業担当者の業務プロセスを改善して、顧客リストの更新を絶対に行うようなプロセスに作り変えることです。これにより、顧客リストの更新をもれなく行うことができます。
2つ目はスモールスタートで効果を実感してもらう方法です。効果を実感してもらうことで営業担当者が自主的に顧客リストを更新してくれるようになるでしょう。
このようにメールマーケティングツールを使いこなせるようになるには多くの関係者が一体となってメンテナンスをする必要が出てくるようになります。この問題を解決するためには、更新対象者を限定する、スモールスタートを行う、絶対に更新するプロセスを確立する等様々な方法があります。
それぞれの方法によって関係者は変わってくるので、自社の状況に応じて、運用可能なツールを選ぶようにすると良いでしょう。
機能(とくに顧客リストの更新しやすさ)
機能ももちろん重要です。配信可能件数やステップ管理など業務に直接関与している機能に関してはよく確認するでしょう。その中で特に見落としやすいのが顧客リストと配信リストの管理と連携です。
基本的には顧客リストと配信リストは別々のデータベースで管理するべきでしょう。しかし、その一方で顧客リストをどのように更新するか、配信リストとどのように整合性をとるかということが課題になります。
多くの場合、顧客リストは手動登録ないしはCRMシステムなど他の顧客情報管理システムなどから連携されてくることになるでしょう。さらに、配信リストまでも手作業でメンテナンスすることになると多くの工数がかかることが見込まれます。
この顧客リストの更新と配信リストの更新をどこまで効率よく行えるかは、多くの会社にとって課題となると言えます。そのため、自社のメールマーケティングツール以外の顧客管理システムとの親和性や配信リストの管理方法を入念に確認し、自社に合ったツールを選ぶようにすると良いでしょう。
価格
価格もメールマーケティングツールを選ぶ上では重要な要素になるでしょう。無料ツールや安いツールを利用する場合できることが限られます。また、サポート体制なども手薄になるでしょう。
しかし、安くても十分なケースもあります。それは自社の目的とする機能がすべてそろっている場合です。その場合にはわざわざサポートやそれ以外の機能が手厚い他のサービスを選ぶ必要はありません。
サービスを選定する際には、まずは自社の必要な機能をリストアップしましょう。特に将来性を見据えて、拡張する前提で検討することが重要です。そのうえで、それらの機能を満たすサービスを選定し、導入するようにしましょう。あまりにも費用が高額となってしまい導入が難しい場合には優先順位が低い機能を他の方法で代替できないか検討を行い、安いサービスが導入できないか検討してみると良いでしょう。
メールマーケティングツールを効果的に使うには
ここまでメールマーケティングツールの種類や選定ポイントを紹介しました。次はどのようにしたらメールマーケティングツールを効果的に利用できるか紹介します。
メール配信を仕組み化する
1つ目はメール配信に関するプロセスを仕組み化することです。メールマーケティングツールを導入する目的にはミスの低減や省力化等様々な理由があるかと思いますが、どのような場合においても目的を意識して
- どの部分を効率化・省力化したいのか?
- どのように効果を上げていくのか?
という二つの観点を徹底して検討することが重要です。そのためキーワードとなるのが仕組み化です。自社の解決したい問題を仕組み化することで、省力化や効率化、ミスの削減など様々な効果を生み出すことができます。例えば、分析作業に注力したいのであれば、開封率やクリック率を自動で算出し、その結果から購買率を求められる機能を仕組み化してしまえば、多くの時間を省くことができます。まずは、メール配信において、お客様が重要と考えるプロセスを仕組化して省力化を目指しましょう。
顧客リストと配信リストを連携する
次に効果的にメールマーケティングツールを利用するために重要なポイントは、顧客リストと配信リストの整合性をどのようにとるかという点です。
顧客リストから配信リストを作成することが基本となりますが、場合によっては配信リストから顧客リスト側に情報を戻す必要も出てきます。
メール配信担当者として業務をされたことがある方であれば、最新のデータをもとにメール配信するために、顧客リストを誰が・どのようにメンテナンスして、どのタイミングで配信リストに反映するのかといった課題に直面されたことがあるのではないかと思います。
ここの顧客リストと配信リストの連携イメージをしっかり具体化しておかないと、正しい配信リストをもとにしたメール配信や配信結果を元にしたマーケティングや営業活動を行えなくなってしまいますので、注意が必要です。
理想的には顧客リストから自動で配信リストが作られることであり、購買情報などの他のデータと連携して、自動抽出できる仕組みを立案できると良いでしょう。
まとめ
ここまでメールマーケティングツールについて紹介してきました。理想はほぼ全自動でCRMなどの顧客管理システムと連動をして自動で配信リストを作成、メールのテンプレート化などによりスムーズなメール文作成が出来ることですが、いきなりこのレベルを実現する必要はありません。まずは導入してみて、使い勝手を確認してみる、一部のプロセスの省力化を検討してみるということでも良いでしょう。しかし、ツール選定時には仕組みを一から見直さなければならないといったことにならないようなツールを選ぶように意識をしておくことをお勧めします。
自社の状況に応じて、こんな仕組みを使って、最終的にはここまで実現しようといった具体的なイメージをもってもらえれば、今回の記事はお役にたったということになると思います。