すべて表示する
エンタープライズ営業とは?
エンタープライズ営業とは、主に大企業や大口顧客を対象とした営業活動・営業スタイルのことで、その最大の特徴は、複雑な意思決定プロセスと長期間にわたる商談プロセスです。
SMB営業(中堅・中小企業向けの営業)活動では、決裁者と直接交渉できることも多く、比較的短期間で成約に至るケースもあります。しかし、エンタープライズ営業では、扱う商材による違いはあるものの、利用部門、購買部門、システム部門、法務部門、経営層など複数の利害関係者との調整が必要になり、商談の進行には数カ月から1年以上かかることも珍しくありません。
なお、「大企業」向けの活動がエンタープライズ営業といっても、単に従業員数や売上規模だけで分類されるわけではなく、たとえ規模が小さくても、意思決定プロセスが複雑で、利害関係者が多い企業や、導入に慎重な姿勢をとる組織もエンタープライズ営業と同じ活動が求められることもあります。
また、エンタープライズ営業は、特定の営業担当者の経験や人脈に依存することが多く、チームでのマネジメントやノウハウの継承が難しいという特徴も持っています。
結果として、営業プロセスが標準化されず、組織全体での効率的な営業活動が困難になっています。しかし、近年では SFAツール(営業支援ツール)やCRMツール(顧客関係管理)の活用によって、営業活動の可視化とデータ活用が多くの企業で進んできました。エンタープライズ営業の領域でも、適切なマネジメントを行うことで、営業生産性の向上やノウハウの共有を実現する企業が増えてきています。
ここまで説明してきたようにエンタープライズ営業の実践には、時間や労力、独自のノウハウ、マネジメント基盤などが必要となるため、自社への導入には二の足を踏む企業も多いのが現実です。
しかし、顧客としてみた大企業は、一度導入した製品やサービスを簡単には切り替えない傾向があり、他の事業部や関連会社への横展開も期待できます。大企業と信頼関係を構築し、顧客が求める価値を提供できれば、安定した売上や収益の確保につながるため、多くの組織が注目している営業スタイルといえます。
エンタープライズ営業が求められる状況
それでは、エンタープライズ営業が求められる状況にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここではよくある3つの状況を説明していきます。
成長戦略としてのエンタープライズ営業
企業の成長戦略の中で、エンタープライズ営業へのシフトが求められることがあります。SMB市場での市場拡大が限界を迎えた際に、新たな市場として大企業向けの市場への展開を狙うような状況です。
たとえば、クラウドサービスを提供する企業がSMB市場向けに成功した後、より大きな契約規模と収益の拡大・安定性を求めてエンタープライズ向けのプランを展開するケースが増えています。
このような状況では、営業活動を変化させるだけではなく、製品・サービスもエンタープライズ市場向けに変化させていく必要があります。
SMB市場に素早く展開するには、特定の業務や業界に特化したサービスが有利となりますが、エンタープライズ市場では、特定の業務だけ改善しても効果が限定的となることが多く、顧客の業務プロセス全体を最適化する製品力・提案力が求められます。
企業の成長とともにマーケティングや営業スタイルを変え、エンタープライズ市場への適応を進めることが重要です。
営業生産性と利益の向上を実現するエンタープライズ営業
エンタープライズ営業は、営業生産性と利益率の向上を実現するために導入が検討されることもあります。
一般的に、エンタープライズ営業により獲得できる案件は単価が高く、契約後の継続性が期待できるため、単発の取引よりも利益率が向上する傾向があります。
また、営業の生産性という観点では、大口顧客との関係を深めることで、少ない案件数でも高い売上を確保できるメリットがあります。たとえば、従来は10社に対する契約で売上を確保していたところ、エンタープライズ営業によって2~3社の契約で同等の売上を確保できるようになることもあります。
このようなことから、営業組織の人的リソースを増やすことなく、売上や利益を拡大できる可能性が考慮され、エンタープライズ営業へのシフトを検討する企業が増えています。
大企業との取引が自然に増えてきている状況
企業が成長するにつれて、大企業との取引が自然と増えてくることはよくあります。
たとえば、SMB市場向けに提供していた製品・サービスが、大企業の部門単位で導入されるようになり、徐々に全社展開の話が持ち上がるといったケースです。
このような状況では、意図しない状況への対応から、意図的にエンタープライズ市場での活動に営業戦略を変化させていかないと、SMB向けの商談と比べて受注率が上がらず、営業生産性が低下してしまう可能性があります。
エンタープライズ営業でSMBと同等以上の営業生産性を実現するためには、大企業の意思決定プロセスの理解、製品のカスタマイズ・価格交渉や契約条件の柔軟性、導入後のサポート体制の強化などが必要です。
このような準備を怠ると、せっかくの大企業からの引き合いをうまく受け止められず、機会損失につながってしまいます。自然に大企業との取引が増えているタイミングこそ、エンタープライズ営業の本格的な導入を検討すべき状況といえるでしょう。
エンタープライズ営業とSMB営業の違い
ここまでの話の中でエンタープライズ営業の特徴について触れてきていますが、改めてSMB営業と比較しながらその特徴を詳しくみていきましょう。
比較項目 | SMB営業 | エンタープライズ営業 |
対象企業数 | 対象企業数:大 | 対象企業数:少 |
意思決定プロセス | 関係者:小 | 関係者:大 |
リードタイム | 数週間~数ヶ月での受注が一般的で、営業活動のスピードが重要 | 数か月~1年以上かかることもあり、長期的な関係構築が必要 |
営業活動の難易度 | 比較的シンプルな営業活動で、標準化が容易 | 高度な提案力、業界知識、経営層との交渉力が必要で標準化が難しい |
規模と横展開の可能性 | 単発契約が多く、追加導入や横展開の可能性は低め | 1件あたりの商談規模が大きく、アップセル・クロスセル、他事業部やグループ企業展開の可能性あり |
1.対象顧客数の違い
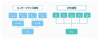
SMB市場は企業数が多く、幅広い業種・規模の企業が存在します。一般的に、営業活動の対象となる企業数が多いため、多くのリード(見込み顧客)に幅広くアプローチし、顧客情報を獲得できた中から育成・見極めを行い優先度をつけて営業活動を行うという徐々に絞り込んでいく活動が行われます。
一方、エンタープライズ市場は対象企業数が限られるため、数多くの企業に幅広くアプローチがすることができません。そのため、自社の強みを活かせる企業にさらに絞り込み、特定の業界や企業グループに深く入り込んでから横展開を狙うような活動が行われます。
2.意思決定プロセスの違い
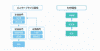
SMB企業では、意思決定者が経営者または数名のキーパーソンであることが多く、商談の進行がスピーディーです。トップダウンで決定されることが多いため、意思決定者が求める価値や予算感を把握して、素早く価値の訴求を行うことが重要となります。
エンタープライズ企業では、意思決定に複数の部門(利用部門、IT、調達、法務、財務、経営層など)が関与し、稟議やコンプライアンスチェックなどの厳格な承認プロセスを経る必要があります。そのため、営業担当者は顧客内のキーマンを特定して提供価値を伝えるだけでなく、各関係者のニーズを満たす提案を行うことが求められます。
3.受注までのリードタイムの違い
SMB営業では、意思決定プロセスがシンプルなことや取引規模が小さいことから、比較的短期間での成約が可能です。数週間から数ヶ月で契約が決まることが一般的です。
エンタープライズ営業では、受注までのリードタイムが長いことが特徴です。特に、これまで取引のなかった企業への活動の場合には、認知向上や情報提供といった地道な活動を行い、競合との明確な差別化を行うことも必要となるため、年単位での長期的な活動が求められます。さらに商談が進んでからも、社内の承認プロセスや価格/契約交渉に時間がかかることも多くなりがちです。
4.難易度の違い
SMB営業では、企業が抱える課題が明確であったり、これまで手を付けていない課題を解決するために新たな製品やサービスを検討することが多くなります。そのため、解決策も基本的な内容で事例も多いため、提案活動は比較的シンプルなプロセスとなり、標準化も容易となります。
エンタープライズ営業では、基礎的な課題は解決済みであることが多く、求められるのはより高度な解決策や部門横断での全社的な課題解決です。そのため、顧客企業が所属する業界動向や他社事例、企業文化から発生する独自の課題、これまでの経緯など企業の内部事情を深く理解し、各ステークホルダーに適切な情報を提供しながらプロジェクトを推進する必要があります。これらのことから、エンタープライズ営業の提案活動には非常に高度な専門知識や経験、人脈が求められ、営業活動の属人性が高くなりがちです。
5.商談規模と横展開の可能性
SMB営業では、単発の取引が多く、急激に成長するベンチャー企業でない限り、製品・サービスを利用する社員などが増えるスピードも遅いため、リピートや追加契約の可能性が低くなりがちです。求める課題解決も基本的なものが多くなるため、契約単価もエンタープライズに比べると小さくなり、顧客数を増やして売上を伸ばすモデルが主流になります。
エンタープライズ営業では、所属する社員数や行われているビジネスが大きいため、1件あたりの商談規模が大きく契約単価が高くなります。また、クロスセルやアップセル、グループ企業への横展開などが期待できる点が魅力といえます。例えば、1つの事業部で導入された製品が、他の部門や海外拠点へ展開されるケースもあります。
エンタープライズ営業組織の立ち上げ・強化に求められる要素
ここまではエンタープライズ営業の特徴や求めらる状況を整理してきましたが、ここからは実際にエンタープライズ営業組織の立ち上げや強化を行う際の要素についてマインドセット、組織力、個人スキル、営業マネジメントの違いという観点から、エンタープライズ営業に求められる要素を整理します。
1.エンタープライズ営業に求められるマインド
エンタープライズ営業は、SMB営業とは異なり、短期間で成果を出すことが難しく、長期的な関係構築が求められる営業スタイルです。そのため、以下のようなマインドセットが必要です。
・長期視点で顧客と関係を築く姿勢
エンタープライズ営業では、契約までに数年かかることも珍しくありません。その間、短期的な成果だけでなく、「顧客と中長期的にどのような価値を創出できるか」という意識が重要です。
・顧客のビジネスを深く理解する姿勢
SMB営業では製品の機能や価格に関する提案が中心となりがちですが、エンタープライズ営業では、顧客の事業課題や戦略を理解し、それに合致する形でソリューションを提案する力が求められます。
・社内外のステークホルダーを巻き込む力
大企業との取引では、1対1の営業関係ではなく、複数の関係者が関与する「チーム対チーム」の構図になることが一般的です。そのため、一人の営業担当者だけで情報提供や提案活動を完結することは難しく、社内では技術部門や製品チーム、カスタマーサポート部門などを巻き込み、顧客側でも情報システム部門や現場部門、経営層など、さまざまばステークホルダーとの調整が求められます。組織を動かすリーダーシップや調整力、巻き込み力が重要な要素となります。
2.エンタープライズ営業に求められる組織力
エンタープライズ営業で成果を上げるには、個々の営業担当者のスキルや能力だけでなく、組織全体での協力体制の構築が不可欠です。具体的には以下のような部門との連携が必要となります。
・マーケティングとの連携
エンタープライズ営業では、ターゲット企業絞り込んだ上で、その企業に様々な角度からアプローチするためのマーケティング活動が必要となります。マーケティングと営業が連携し、ターゲット企業のリードを獲得し、適切なコンタクトを図るための計画・施策実行の体制を整えることが重要です。
・カスタマーサクセス(サポート)との連携
エンタープライズ営業では、契約獲得後の導入・活用支援や運用サポートが成功の鍵になります。提案時に提示した提供価値が実現されて初めて、クロスセルやアップセルが実現できることを忘れないようにしましょう。営業が契約を取った後、カスタマーサクセス(サポート)やプロジェクト管理チームとスムーズに連携し、組織が一丸となって価値提供を行う体制が必要です。
・技術・プロダクトチームとの連携
エンタープライズ案営業では、顧客の要望に応じたカスタマイズが必要になることが多くなり、営業部門単独では対応はできません。技術チームと密に連携し、顧客ニーズに応えられる体制を整えることが求められます。また、重要顧客だからといってすべての要望に応えるだけでなく、出来ないことや時間がかかることなどもしっかりと説明し、社外と社内の調整を図ることが必要となります。
3.エンタープライズ営業に求められる個人スキル
エンタープライズ営業では、通常の営業スキルに加え、以下のような高度なスキルセットが求められます。
・アカウントマネジメント力
エンタープライズ営業では、1つもしくは少数の企業に深く入り込み、自社が提案するべき部門を把握して、適切な課題解決について提案を行う必要があります。そのためには、業界特性や業界内での企業のポジションの把握、中長期・短期的な課題、企業文化・組織構造や独自の意思決定プロセスを把握し、戦略的なアプローチを計画・実行するアカウントマネジメント力が求められます。
・経営層とのコミュニケーション力
SMB営業では現場レベルの担当者とのやり取りが中心ですが、エンタープライズ営業では、最終的に経営層や事業部長クラスへの提案や交渉が求められます。顧客企業の経営戦略を理解した上で、投資対効果や課題に着手するべきタイミングについて、経営層の視点を持って伝えることができるコミュニケーション力が重要です。
・提案・コンサルティングスキル
競争が激しいエンタープライズ市場では、単に製品・サービスの説明を行うような営業活動ではなく、顧客の課題を解決するコンサルタントとしての役割が求められます。業界動向や市場環境を理解し、顧客の経営課題を解決する提案力を磨くことが不可欠です。
・交渉力
契約に至るまでの過程では、利用部門や意思決定者だけでなく、調達部門との価格交渉や法務部門との契約内容の調整などの複雑な交渉が必要になります。顧客の要望を踏まえつつ、自社にとって最適な条件で合意を形成するスキルが求められます。
4.SMB営業とは異なる営業マネジメント
エンタープライズ営業のマネジメントでは、SMB営業のマネジメントとは大きく異なるアプローチが必要になります。以下の点を意識したマネジメントを行いましょう。
・短期と中長期の視点のバランス
SMB営業では、「月の新規契約数」や「受注率」などの短期KPIが重視されますが、エンタープライズ営業では「アカウントプランの進捗度」「キーパーソンの把握状況」「ターゲット内シェア」など、中長期的な指標を組み合わせた評価が必要となります。
・案件管理と情報共有の徹底
エンタープライズ営業では、1件ごとの商談規模が大きいため、1つの失注で大きく事業計画が崩れてしまう可能性があり、それぞれの案件の進捗状況や失注リスクを把握することが不可欠です。属人性を排除するためにも、SFA/CRMツールを活用し、データをもとに現状把握や受注予測を行い、営業プロセスを適切に管理する体制が求められます。
・組織横断の協力体制の確立
エンタープライズ案件は営業部門単独で活動を完結できないため、マーケティング、カスタマーサクセス(サポート)、技術部門、法務部門など社内の各部門と連携する体制を整えることが重要です。部門横断での情報共有会議やツールを使った効率的な情報交換を行うことが求められます。
エンタープライズ営業実践のポイント
ここまで説明してきたエンタープライズ営業の特徴や求められる要素をもとに、実践する際の重要なポイントを4つにまとめてみました。
1.差別化ポイントを押さえた適切なターゲティング
エンタープライズ営業では、ターゲット企業の選定と差別化戦略が成功の鍵となります。市場全体を対象にするのではなく、自社の強みが活かせる特定の業界や企業群を狙うことが重要です。
特にこれからエンタープライズ営業組織を立ち上げる場合には、ターゲットとする企業が所属する業界や企業規模などによって必要な人材なども変わることがありますので、慎重なターゲット選定が必要となるでしょう。
すでに大企業との取引やコンタクトがある場合には、その企業をターゲットとしつつ、適切な営業活動を確立し、徐々に他の企業へのアプローチを行うとよいでしょう。
2.アカウントプランの策定と実行
大企業との取引では、ターゲットとなる企業ごとに異なる戦略が必要です。そのため、ターゲット企業ごとにアカウントプランと呼ばれる攻略プランを策定し、プランに基づいた活動の実施とマネジメントが求められます。
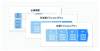
アカウントプランとしてまとめる項目例としては、
- 顧客や所属業界に関する基本的な情報
- 組織構造と意思決定プロセス
- 顧客の短期・中期・長期の目標と戦略
- 顧客の課題とニーズ
- 提供できる価値と解決策
- アクションプラン
などが挙げられます。
多数の企業に対し、最初から完璧なアクションプランを策定して適切なマネジメント行うことは困難であるため、顧客や項目を絞って運用可能な範囲から着手するようにしましょう。
また、アカウントプランと共にエンタープライズ営業に欠かせないのが、バイヤー相関図(リレーションマップ)です。
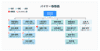
バイヤー相関図とは、ターゲット顧客内の人間関係や影響関係を一目で可視化した図表です。公開された組織図では捉えきれない、ステークホルダー同士の力関係や意思決定における役割分担を把握するために用いられるので、顧客とコミュニケーションを進めながら完成度を高め、顧客企業内の変化も捉えられるようにしましょう。
アカウントプランの策定手順や各項目の詳細、バイヤー相関図については本シリーズの別のセッションで解説を行います。
3.定量データと定性データを活用したマネジメント
エンタープライズ営業のマネジメントでは、SFA/CRMツールを活用したデータドリブンなアプローチと、営業担当者の定性的な情報を活かした戦略立案の両方がもとめられます。
・定量データの活用
エンタープライズ営業では、長期的な活動が必要となるため、各営業担当社がアカウントプランに基づき適切な活動を行っているのかを企業数、訪問数、案件数、受注数、売上金額といった数値情報をもとにマネジメントする必要が出てきます。
営業担当者が重要顧客に定期的に訪問できているか、個別の案件の進捗や受注見込みと営業目標に乖離がないかなどを可視化することが求められ、そのようなマネジメントを実現するツールとして、SFA/CRMツールが導入・活用されます。
定量データはターゲティングにも重要な情報となるため、データの一元化・蓄積はエンタープライズ営業に欠かせません。
・定性データの活用
顧客の経営課題や意思決定プロセス、社内政治、決裁者の本音など、数値化が難しい情報が定性データです。
前述のアカウントプランなどは、定性情報の集大成と呼ぶべきものですが、アカウントプランを作成するための情報は、顧客との日々のコミュニケーションやインターネットなどを介した情報収集によって得られるものです。
ただし、定性データは、どのような形でまとめるかが決まっていないことが多く、担当者の主観や表現に依存する部分もあるため、定量データと比べて属人化しやすいデータといえます。
顧客との関係性や案件の進捗状況によって、どのような定性情報を収集し、どのような形で蓄積すべきなのかを組織として決定して、管理・活用していくことが求められます。
![[基礎学習] エンタープライズ営業とは](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/jp/crm/academy/master3-banner-lazy.png)